情シスが行うべき監視業務とは?目的や具体的な仕事内容を解説
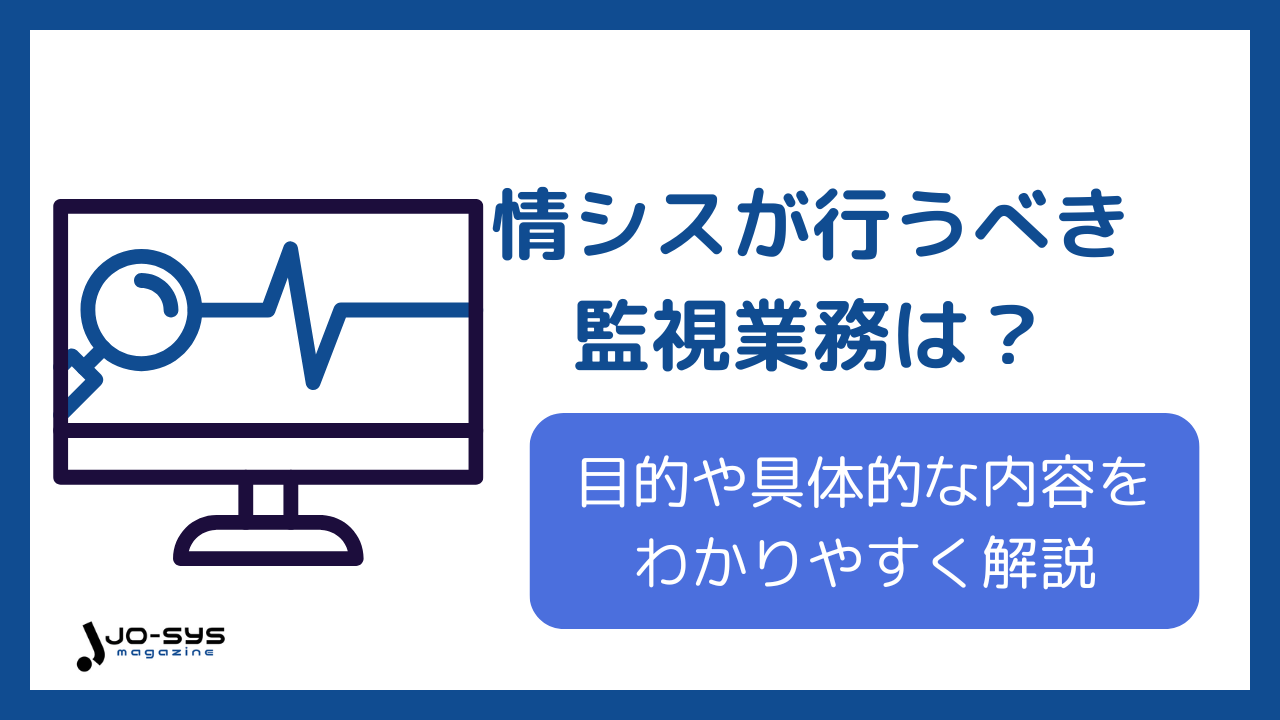
システム障害が発生してもすぐに原因が特定できない
情シスの監視業務って具体的に何するの?
監視業務を怠るとどうなるの?
企業のITインフラを支える情報システム部門にとって、監視は重要な業務です。
しかし実際には、「何をどこまで監視すればいいのか」「どんな仕組みで異常を検知するのか」があいまいなまま運用されているケースは少なくありません。
この記事では、情シスがおこなうべき監視業務の全体像を解説します。
サービス監視やサーバー監視、インフラ監視などの具体的な内容から、監視の目的、怠った場合のリスクまでを整理し、すぐに実務で役立つ知識を身につけられる内容です。
情シスが行うべきシステム監視・IT監視
情シスがおこなうべきシステム監視・IT監視業務は、以下のとおりです。
それぞれ詳しく解説します。
サービス監視 | アプリやWebサイトが正常稼働しているか確認する
サービス監視は、ユーザーが利用するアプリケーションやWebサイト、システム基盤のサービスが正常に動作しているかを確認する監視業務です。
障害を未然に防ぎ、異常が発生した際には即座に検知・通知して業務停止を防ぐことが主な目的です。
企業システムは複数のサーバーやプログラムが連携して稼働しており、一部が停止するだけで全体のサービスに影響が及ぶことも少なくありません。
そのため、DNS・ロードバランサー・アプリケーションサーバーなどの基盤を対象に、24時間体制で監視を行うことが求められます。
サーバー監視 | CPU・メモリ・ディスク使用率をチェックする
サーバー監視とは、システムを構成する各サーバーの稼働状況を常時監視し、リソース使用率の異常や故障の兆候を早期に検知する業務です。
監視対象はCPU・メモリ・ディスクなどのリソースが中心であり、使用率が閾値を超えた場合にアラートを発報することで、システム停止を未然に防ぎます。
たとえば、CPU使用率が90%を超える状態が継続すれば、プロセスの暴走やリソース不足が原因であると推測できるでしょう。
また、稼働中のプロセス数やI/O待ち時間も併せて監視することで、ボトルネックを正確に把握できることも、サーバー監視をおこなう目的です。
インフラ監視 | 通信経路や帯域の異常を検知する
インフラ監視とは、ネットワーク機器や通信経路の状態を確認し、帯域の利用率や通信遅延、パケットロスなどの異常を検知する業務です。
企業のITシステムは、サーバー・ルーター・スイッチ・ファイアウォールなどのネットワーク機器を通して構築されています。
どれかひとつでも不具合が発生すると、全体の通信が滞り、サービスの停止や遅延につながるおそれがあります。
そのため、インフラ監視はシステム全体の「血流」を管理するような役割を持ち、安定したネットワーク通信を維持するうえで欠かせません。
死活監視 | 対象システムが生きているか自動的に確認する
死活監視とは、ネットワーク機器やサーバーに定期的に信号を送り、応答があるかどうかを確認する監視方法です。
応答が返ってくれば「正常」、応答がなければ「異常」と判断し、異常を検知した場合にはすぐにアラートを出して対応をおこないます。
情報システムを構成する機器類の障害発生状況等を把握するために、機器の通信状態の変化や再起動の状況を監視する。
※引用:内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 解説書」
死活監視によって、サーバーやネットワーク機器の停止、通信断、再起動といったトラブルを自動的に検出できるため、情報システムの安定運用を支える基本的な監視手法といえるでしょう。
リソース監視 | システムリソースの逼迫を早期に把握する
リソース監視とは、サーバーやネットワーク機器などのシステムリソース(CPU、メモリ、ディスク容量、ネットワーク帯域など)の使用状況を継続的に確認し、逼迫の兆候を早期に検知する監視手法です。
リソースはシステムの「体力」ともいえる存在であり、過剰な負荷や容量不足を放置すると、処理遅延やシステム停止といった深刻な障害につながります。
そのため、リソース監視は障害の予防と性能維持のための基盤的な取り組みとして、情シスが優先的に整備すべき監視項目です。
リソース監視では、以下のような項目を重点的に確認します。
| 監視対象 | 内容 | 対応策 |
|---|---|---|
| CPU使用率 | プロセス負荷やスレッド数を監視 | 負荷分散・プロセス調整 |
| メモリ使用率 | 利用量や空き容量を監視 | アプリ最適化・再起動 |
| ディスク容量 | 空き容量とI/O速度を確認 | 不要データ削除・増設 |
| ネットワーク帯域 | 通信量・転送速度を可視化 | 通信経路最適化・QoS設定 |
リソース監視を定期的に実施することで、トラブルの「兆候」を数値で把握でき、障害発生を未然に防ぐことができます。
スクリプト監視 | 定期処理や自動化スクリプトの実行を監視する
スクリプト監視とは、定期的に実行されるバッチ処理や自動化スクリプトの実行結果を監視し、正常に完了しているかを確認する監視手法です。
企業のシステム運用では、バックアップ、データ転送、ログ整理、レポート生成など、多くの業務がスクリプトによって自動化されています。
スクリプトがエラーで停止した場合、業務データの欠損やバックアップの失敗など、業務継続に直結する重大トラブルを引き起こす可能性があります。
スクリプト監視を導入することで、担当者が手動で確認しなくても、自動化処理の失敗を即時に検出することが可能です。
システム監視 | システム全体の稼働状況を可視化する
システム監視とは、サーバー・ネットワーク・アプリケーション・ミドルウェアなど、複数の要素から構成されるシステム全体の稼働状況を一元的に把握・可視化する監視手法です。
個別の監視(サービス監視、サーバー監視、リソース監視など)は特定範囲の状態を確認するのに有効ですが、複雑化したシステム環境では、それらを統合して全体の動きを俯瞰的に捉えることが重要になります。
そのためシステム監視は、複数の監視データを集約・分析し、異常を即座に検知・通知するための中枢的な仕組みとして機能します。
システム詳細監視 | 特定プロセス・ログ・ミドルウェアの状態を細かく分析する
システム詳細監視とは、システム全体の監視の中でもより深いレベルで、特定のプロセス・ログ・ミドルウェアの挙動を細かく分析する監視手法です。
アプリケーションやデータベースなどの内部状態を監視し、エラーや性能低下の兆候をいち早く検出することで、障害の根本原因を迅速に特定できます。
たとえば、メールが指定の時間内にサーバーに到達できているか、ログが想定通りの挙動となっているかなど、より実動作に近い内容の監視をおこなうのが特徴です。
トライアル申込者全員に
「IT管理に使える4大テンプレート」
無料プレゼント!
- 💻 IT資産管理台帳
- 🧾 PC利用規定テンプレート
- 🔐 パスワードポリシーサンプル
- 🌐 IPアドレス管理表
👉 トライアルに申し込む
情シスが監視を行う4つの目的を理解しよう
情シスが監視をおこなうのには、以下のような目的があります。
障害を予防して業務停止を未然に防ぐ
情報システムの監視は、障害が発生してから対応するのではなく、発生前に兆候を捉えて防止することを目的としています。
業務を支えるシステムは常に膨大なデータを処理しており、わずかな遅延やリソース逼迫がやがて深刻な障害につながることもあります。
そのため、監視は「異常が起きたことを知るため」ではなく、「異常を起こさないため」に実施することが重要です。
障害を予防するために、監視では次のような指標を確認します。
- 処理時間(TAT):処理の開始から完了までを計測し、遅延が発生していないか確認する
- トランザクション量(スループット):処理件数を監視し、負荷の増減を把握してリソース利用を最適化する
- 戻り値の妥当性:プログラムが正しい結果を返しているかを確認し、エラーを早期に発見する
- リソース使用率:CPU・メモリ・ストレージなどの利用状況を可視化し、逼迫を未然に防ぐ
たとえば、金融機関ではスマートフォン取引の急増による記憶領域不足が障害の原因となった事例があります。
このようなケースでは、リソースの使用状況を継続的に監視し、容量不足や処理能力の限界を事前に検知しておくことが効果的です。
事前に障害を検知して、発生を予防することが情シスの監視業務における目的のひとつであると認識しておきましょう。
参考:総務省「地方公共団体における 情報セキュリティポリシーに関する ガイドライン(令和6年10月版)」
金融庁「金融機関のシステム障害に関する 分析レポート」
障害発生時の原因特定につながる
システム監視で取得されるログや記録は、障害発生時の原因を迅速かつ正確に特定するための重要な証拠です。
監査ログを分析すれば、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃の侵入経路、実行コマンド、アクセスファイルなどを追跡できます。
また、アクセスログや稼働ログ、障害出力ログを一定期間保存しておくことで、事後の原因分析や再発防止策の立案が容易になります。
金融庁の金融機関におけるシステム障害の事例では、必要な情報を取得していなかったために原因特定が遅れたケースもあり、ログ取得と保管体制の整備が重要です。
記録の可視化と分析を徹底することが、迅速な障害対応とシステムの信頼性向上につながります。
サービスの正常性を常時確認し信頼性を維持する
監視の目的の一つは、サービスの可用性と完全性を常に確認し、利用者からの信頼を維持することです。
システムは常時稼働しているため、不正アクセスや不正プログラムによる攻撃を防ぎながら、正常な稼働状態を保つ必要があります。
また、適切な監視体制を維持することで、システムの安定稼働だけでなく、地域社会や利用者に対する安心感と信頼性の向上にもつながります。
監査・セキュリティ対応にも活用できる
監視で収集したログやデータは、システムが適切に運用されているかを検証する証跡となり、内部統制や法令遵守の根拠として活用できます。
主な活用ポイントは次のとおりです。
- 監査対応と証跡管理
- セキュリティポリシー遵守の検証
- 不正行為の検知
さらに、ログを定期的に点検・分析することで、不正アクセスや不正通信の有無を確認し、再発防止策の立案にもつながります。
このように、監視はセキュリティ維持の手段であると同時に、監査対応とリスク管理を支える防御基盤として機能します。
情シスがシステム監視を怠るとどうなる?
情シスがシステム監視を怠ると、以下のようなリスクがあります。
初動対応が遅れる
システム監視を怠ると、異常の発生をリアルタイムで検知できず、ユーザーからの問い合わせや苦情で初めて問題に気づくケースも少なくありません。
その結果、初動対応が遅れ、被害が拡大するリスクが高くなります。
監視によってアラートを自動発報し、担当者へ即時通知する仕組みを整えることで、障害発生から対応開始までの時間を最小化できます。
サーバーダウンなどの障害につながる
システム監視を怠ると、サーバーやネットワーク機器の異常を検知できず、結果としてサーバーダウンなどの重大な障害に発展する可能性があります。
CPUやメモリの使用率、ディスク容量などのリソース逼迫を監視していなければ、負荷が限界に達してから初めて障害が発生し、業務システムが停止するリスクが高まります。
監視を行っていれば、こうした兆候を早期に発見し、リソースの増強や再起動などの preventive 対応でトラブルを回避することが可能です。
トライアル申込者全員に
「IT管理に使える4大テンプレート」
無料プレゼント!
- 💻 IT資産管理台帳
- 🧾 PC利用規定テンプレート
- 🔐 パスワードポリシーサンプル
- 🌐 IPアドレス管理表
👉 トライアルに申し込む
まとめ | 情シスの監視業務は事業の正常運用に不可欠
情シスにとって監視業務は、単なる障害検知ではなく、企業の事業継続を支える中核的な運用活動です。
サービス監視・サーバー監視・インフラ監視・死活監視などを通じて、潜在的な障害を未然に防ぎ、トラブル発生時には迅速な対応が可能になります。
監視によって得られるログやデータは、障害原因の特定や不正アクセスの検知、監査対応にも活用でき、セキュリティ強化と信頼性維持の両立を実現できます。
自社の監視体制を見直し、アラート通知・ログ分析・自動化ツールの導入を通じて、情シスが本来果たすべき「安定運用の要」としての役割を強化しましょう。
.jpg)

